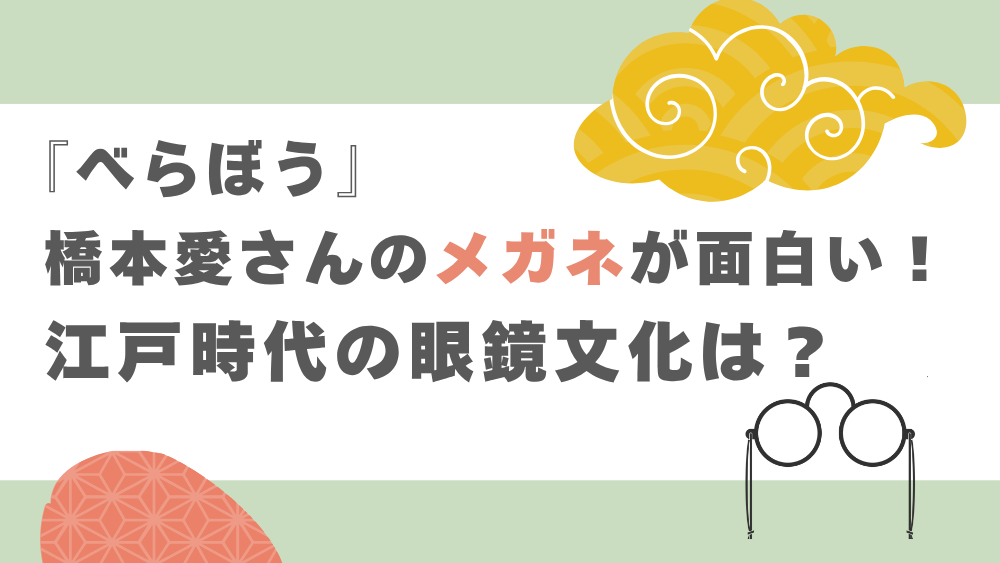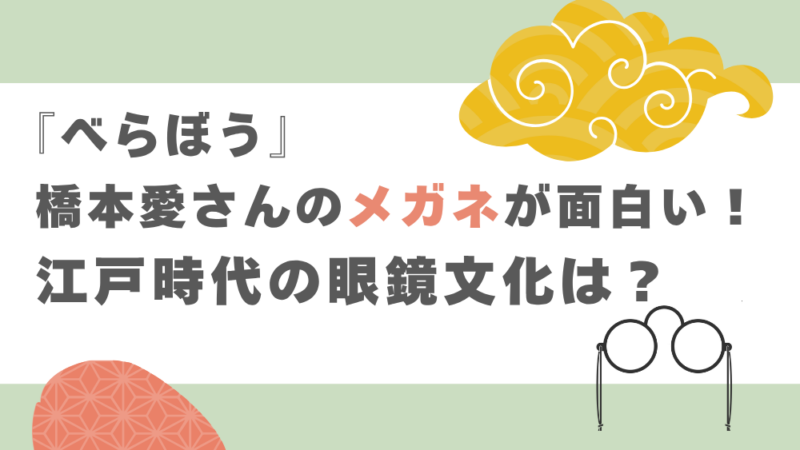
NHK大河ドラマ『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』に登場する、橋本愛さん演じる蔦屋重三郎の妻「てい」。
大河で眼鏡は珍しく、しかも眉間にのせる形。
初めて見たときのインパクトは絶大ですよね。
今回は、ていがかけているメガネの正体を探りながら、江戸時代のメガネ事情やその歴史についてもやさしくご紹介します。
橋本愛さんのメガネが気になる!現代とは違う形は何?
NHK大河ドラマ『べらぼう』で、橋本愛さん演じる妻のていがかけている独特なメガネ。
初めて見た時、とてもインパクトが強くて驚きますよね。
- 黒縁で丸く、レンズ周りが太めで存在感がある
- 顔の半分近くを覆う大きさ
- 眉間寄りの位置で鼻の根元に引っかけるように装着
- 耳にかけるつるがない、紐で支える構造
現代のメガネとは違ってとても不思議で面白い形ですよね。
橋本愛さんのメガネは本当に存在した?
橋本愛さんの形のメガネは本当に存在したのでしょうか?
調べてみると、『べらぼう』の舞台である江戸時代中期に使われていた、実在のメガネが確認できました。
それが「天狗眼鏡(てんぐめがね)」や「支柱式眼鏡」と呼ばれるスタイルのメガネです。
「天狗眼鏡」「支柱式眼鏡」とは?
『べらぼう』の中で、橋本愛さん演じるていが着用しているメガネのスタイルは、江戸時代中期に実際に使われていた「天狗眼鏡」や「支柱式眼鏡」と非常によく似ています。
「天狗眼鏡」「支柱式眼鏡」の特徴
- 鼻に直接のせるのではなく、眉間のあたりに引っかけて装着
- 耳にかけるつるがなく、紐で頭や耳に引っかけて固定
- フレーム素材は鼈甲(べっこう)や真鍮、木材、べっ甲+金属の組み合わせなど
- 装飾性が高く、実用品でありながら身分や知性を表す小道具でもあった
- 用途は老眼鏡(凸レンズ)としての使用が多かったとされています
石川県歴史博物館では、江戸時代中期の天狗眼鏡が貯蔵されています。白べっこう製の支柱式眼鏡で、日本の眼鏡の中では、初期のとても古く高価な貴重なものです。
石川県指定民俗文化財に指定されています。
江戸時代のメガネ事情をリサーチ!日本に眼鏡が伝わった歴史
蔦屋重三郎の妻の「てい」がかけていた、不思議な形の眼鏡──。
そもそも、「江戸時代にメガネってあったの?」と思った方も多いのではないでしょうか。
実は、日本に眼鏡が伝わったのは16世紀半ば、戦国時代のこと。
キリスト教を伝えるために来日した宣教師・フランシスコ・ザビエルが、1551年に周防国(現在の山口県)を治めていた大内義隆に献上したとされるのが、最古の記録とされています。
その後も宣教師や外国人商人たちが、鏡や望遠鏡などと並んでメガネを日本にもたらしました。
最初は一部の権力者や知識層が使っていたようですが、江戸時代に入ると、少しずつ町人文化にも広がっていきます。
『べらぼう』の時代には町人もメガネを手にするように
『べらぼう』の江戸時代中期には、出版文化の発展と識字率の上昇にともなって、読書をする人が増加。
それに伴い、眼鏡の需要も徐々に広まりました。
江戸時代中期は、出版業が発展し、庶民の識字率も上昇していた時代。
この頃、日本では輸入に頼っていたメガネのフレームを国内で製造する動きも出てきました。
材料には真鍮やべっ甲、木などが使われ、形状も「支柱式」や「鼻あてのない丸型」など独自の進化を遂げます。
鼻にひっかけてかける現代風のメガネが定着するのは、もっと後の時代。
江戸期のメガネは、まさにていがかけていたようなメガネを使っていたのですね。
徳川家康もメガネを使用していた
また、歴史的に有名なエピソードとしては、徳川家康が老眼鏡を使っていたことも記録されています。
静岡県の久能山東照宮博物館には、家康が使用していた手持ち式の眼鏡「目器(もっき)」が現在も展示されています。
このように、江戸時代中期にはすでにメガネは存在し、視力を補う道具として一部で使われていたことがわかります。
ていの丸眼鏡も、そんな時代背景を踏まえたリアルな演出だったのですね。
庶民にもメガネは使われていたの?江戸時代に広がった町の眼鏡文化
メガネが日本に伝来してから約85年後、1630年代にはポルトガル船によって大量の鼻眼鏡が日本に輸入されていました。
1637年にはなんと3万個以上もの鼻眼鏡が日本に入っていた記録も残っています。
当初はべっ甲や真鍮製の高価な品として、一部の知識人や富裕層が使用していたメガネ。
しかし、江戸時代中期には徐々に庶民の間にも広がっていきます。
たとえば、1665年に刊行された京都の案内書『京雀』では、四条坊門通(たこやくし通)に「目かねや(メガネ屋)」があったことが記されています。
実際に挿絵も残っており、当時すでに町の中に眼鏡店があったことがわかります。
また、17世紀には国産のメガネ製造も始まり、玉細工職人が眼鏡屋を兼ねていたことも。
このようにして、メガネは少しずつ庶民の生活にも浸透していったのです。